「奇想の系譜」展 [展覧会(日本の絵)]
東京都美術館で、江戸絵画「奇想の系譜」展を見た。
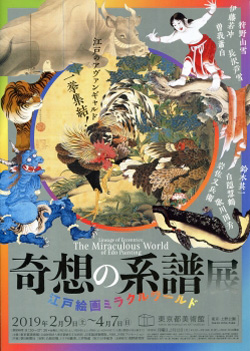
「奇想の系譜 江戸絵画ミラクルワールド」、そこに列挙されている画家たちは、
岩佐又兵衛、狩野山雪、伊藤若冲、曽我蕭白、長沢芦雪、歌川国芳、白隠慧鶴、鈴木其一。
私の好きな其一、若冲、芦雪に「奇想」という言葉はしっくりこない気がしたが、
内容が魅力的だったので行った。前期と後期に分かれているが、前期は見たことの
あるものが多かったので、後期に出かけた。
それぞれの画家に部屋が割り当てられる展示だった。
まずは一番人気の
1、伊藤若冲(1716-1800)
最近、人気が高い若冲。展覧会も、時々あるので、見たことがある作品が多かった。
岩佐又兵衛、狩野山雪、伊藤若冲、曽我蕭白、長沢芦雪、歌川国芳、白隠慧鶴、鈴木其一。
私の好きな其一、若冲、芦雪に「奇想」という言葉はしっくりこない気がしたが、
内容が魅力的だったので行った。前期と後期に分かれているが、前期は見たことの
あるものが多かったので、後期に出かけた。
それぞれの画家に部屋が割り当てられる展示だった。
まずは一番人気の
1、伊藤若冲(1716-1800)
最近、人気が高い若冲。展覧会も、時々あるので、見たことがある作品が多かった。
米国・エツコ&ジョー・プライスコレクションのもので、「紫陽花双鶏図」
「旭日雄鶏図」、「虎図」、「葡萄図」
MIHO MUSEUM所蔵の、「象と鯨図屏風」。
とはいえ、絵に再会すると、ますます親しみが増す感じがする。
「旭日雄鶏図」、「虎図」、「葡萄図」
MIHO MUSEUM所蔵の、「象と鯨図屏風」。
とはいえ、絵に再会すると、ますます親しみが増す感じがする。
最近 発見されたという初期の作品「梔子雄鶏図」 個人蔵
若い頃、30代の作品と推定されている。

若い頃、30代の作品と推定されている。

2、曽我蕭白(1730-1781)
「雪山童子図」 三重・継松寺

雪山童子は、幼い釈迦。修行している時、鬼が唱える経の前半を聞き、鬼に喰われれば
後半を教わることが出来るというので、身を投げ出そうとしているところ。
赤、白、青の画面が美しい。近くで見ると、雪山童子の周りに雪が降っているとわかる。
蕭白の絵は、おどろおどろしさを感じることが多いのだが、この童子はかわいい。
「雪山童子図」 三重・継松寺

雪山童子は、幼い釈迦。修行している時、鬼が唱える経の前半を聞き、鬼に喰われれば
後半を教わることが出来るというので、身を投げ出そうとしているところ。
赤、白、青の画面が美しい。近くで見ると、雪山童子の周りに雪が降っているとわかる。
蕭白の絵は、おどろおどろしさを感じることが多いのだが、この童子はかわいい。
「群仙図屏風」 文化庁 重要文化財 右隻

芸大所蔵の水墨による「群仙図」もあったが、薄墨なので、これよりずっと穏やかにみえた。
3、長沢芦雪(1754-1799)
群猿図襖絵 兵庫・大乗寺 重要文化財
猿たちの仕草や表情がそれぞれ違っていて、面白い。
蘆雪は、応挙の弟子。大乗寺の住職が若い頃の応挙を支援したお礼に、応挙は
弟子たちを率いて大乗寺に行き、襖絵や屏風絵を描いた。

群猿図襖絵 兵庫・大乗寺 重要文化財
猿たちの仕草や表情がそれぞれ違っていて、面白い。
蘆雪は、応挙の弟子。大乗寺の住職が若い頃の応挙を支援したお礼に、応挙は
弟子たちを率いて大乗寺に行き、襖絵や屏風絵を描いた。

「白象黒牛図屏風」 米国・エツコ&ジョー・プライスコレクション
右隻
右隻
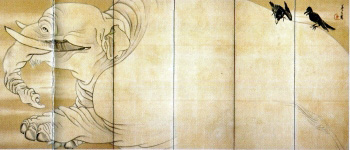
左隻
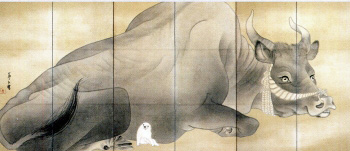
白い象と黒い牛。黒と白の対比。
象の背中にカラスがとまり、牛の足元には、白い仔犬がいる。これも黒と白の対比。
象の背中にカラスがとまり、牛の足元には、白い仔犬がいる。これも黒と白の対比。
4、岩佐又兵衛(1578-1650)
岩佐又兵衛は織田信長に仕えた戦国武将の荒木村重の子である。
「山中常盤物語絵巻」 MOA美術館 重要文化財
牛若丸(後の源義経)の母、常盤御前が牛若丸を追って奥州に向かう途中、盗賊たちに
殺されたので、牛若丸が仇を討つという話。全12巻中、5巻が展示されていた。
胸に刀を突きつけられ、血を流して横たわる御前の姿を生々しく表現していた。
絵巻なので、順に見て行くことになる。
上方に拡大図が示され説明がついていたので、わかりやすかった。
岩佐又兵衛は織田信長に仕えた戦国武将の荒木村重の子である。
「山中常盤物語絵巻」 MOA美術館 重要文化財
牛若丸(後の源義経)の母、常盤御前が牛若丸を追って奥州に向かう途中、盗賊たちに
殺されたので、牛若丸が仇を討つという話。全12巻中、5巻が展示されていた。
胸に刀を突きつけられ、血を流して横たわる御前の姿を生々しく表現していた。
絵巻なので、順に見て行くことになる。
上方に拡大図が示され説明がついていたので、わかりやすかった。
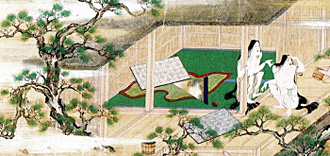
「官女観菊図」 山種美術館 重要文化財
官女たちが牛車の御簾をあげて、道端に咲いている菊を眺めている。
官女たちが牛車の御簾をあげて、道端に咲いている菊を眺めている。

5、狩野山雪(1590-1651)
「龍虎図屏風」 個人蔵
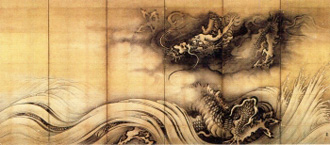

6、白隠慧鶴(1685-1768)
白隠慧鶴は臨済宗の僧。数多くの書画を描いた。
白隠慧鶴は臨済宗の僧。数多くの書画を描いた。
「達磨図」 大分・萬壽寺
80才過ぎに描いた最晩年の絵。目をぎょろりと見開く達磨。赤い僧衣に黒の背景と線が
即興的な絵全体を引き締めている。
80才過ぎに描いた最晩年の絵。目をぎょろりと見開く達磨。赤い僧衣に黒の背景と線が
即興的な絵全体を引き締めている。
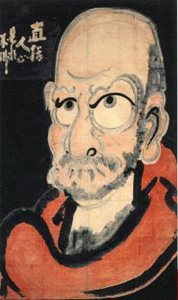
これは、着色の絵だが、作品は、墨絵の方が多かった。
7、鈴木其一(1796-1858)
「百鳥百獣図」 キャサリン&トーマス・エドソンコレクション
これが、この展覧会で一番見たかった作品。初の里帰り展示。
「百鳥百獣図」 キャサリン&トーマス・エドソンコレクション
これが、この展覧会で一番見たかった作品。初の里帰り展示。

びっしりと描きこまれた動物と鳥。若冲の作風を思い出すが、其一の個性が光る。
百獣図では、前景の白い象が目だっている。桐の木には鳳凰が止まっている。
8、歌川国芳(1797-1861)
「宮本武蔵の鯨退治」 弘化4年(1847)頃
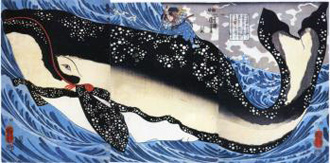
黒と白の対照が明快。鯨の背にのる武蔵の姿はかなり小さい。
盛り上がる波の構図は葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」を参考にしているのだろうか。
個性的な画家たち8人の力作が揃い、見応えがあった。
*会期は7日(日)まで。
*会期は7日(日)まで。



